浸食輪廻とは、自然地理学者のデーヴィスの説で、河川の水の侵食によって、平坦な土地から急峻な渓谷ができ、また平坦な土地になるという地形発達、地形変化のモデルです。地形輪廻ともいいます。
主に川の浸食によって、地形が変っていくサイクルがあるのです。
地盤が隆起し原地形が現れたあとにいくつかのステージを経て、地形が変化していきます。
原地形 → 幼年期 → 壮年期 → 老年期といった過程があります。
幼年期
河川などの浸食、風化によって土地が削られはじめるのが幼年期です。浸食が行われて徐々にV字の谷が深くなり、原地形は失われていきます。

幼年期の例として、アメリカのグランドキャニオンがあります。
壮年期
尾根が鋭く、谷が深い地形である壮年期。河川の浸食で谷が深く削られています。壮年期は早壮年期と満壮年期に分けられることもあります。
日本のアルプスや、ヨーロッパアルプスがその例です。フランスのシャモニを旅したときに撮った写真です。



こちらも同じくヨーロッパアルプスで、スイスの山岳風景です。

老年期
さらに河川の浸食を受け、谷幅が広くなり、山が丸みを帯びるのが老年期です。広がった谷では河川が蛇行します。
準平原
最後には平坦な準平原となります。浸食輪廻の最終段階で、地形面の高さが浸食基準面の近くまで下がり、高低差のない平坦な地形です。
浸食は繰り返される
準平原が隆起すると、また原地形となり、ふたたび浸食輪廻の流れが始まります。これを隆起準平原といいます。
日本の福島県東部に広がる阿武隈高地は、隆起準平原です。侵食を受け、ほぼ平原状を示す広域な地形を山頂部に持つ山地・丘陵です。
 Image by Σ64/Wikimedia Commons
Image by Σ64/Wikimedia Commons
河川による浸食は、山の高いところほど浸食する力が強く、海に近い平野になると浸食よりも堆積がよく起こるようになります。
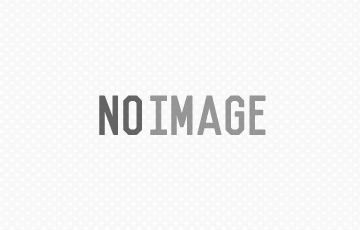










コメントを残す