水無川とは、その名前のとおり水が無い川です。「みずなしがわ」と読みます。
洪水のときには一時的に水の流れができるのですが、ふだんは水が伏流していて、地表には水の流れはありません。
水無川ができるのは扇状地です。
扇状地とは、山の麓に見られる扇状、または半円状の地形のこと。
傾斜があって流れが急ですので、流される土砂のなかで石粒のような大きなものだけが堆積します。砂や泥のようなものは、ここで堆積することはなく、より下流に流れていきます。
砂礫が堆積する土地では、川の水が土地の下にしみこんで、流れが地表には見えなくなります。ふだんは、水の流れがないのですが、大雨が降ったときには水量が増えますから、表面に水の流れができます。
乾燥地域では、乾燥しているがゆえに、ふだんは水が無い、涸れた川があります。ワジと呼ばれていて、川の跡だけあり、大雨が降った洪水のときにだけそこに水が流れて、川ができるのです。
これも水無川の一種です。

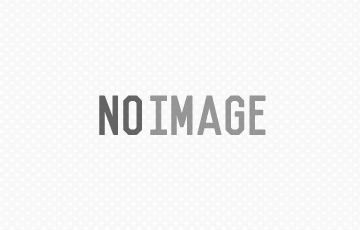










コメントを残す