カルスト地形とは、海底に堆積した石灰岩が隆起し、雨水によって溶食されてできた地形のことです。
溶食とは、岩石が二酸化炭素が混じる水によって溶かされることです。雨水には二酸化炭素が含まれていて、石灰岩を少しずつ溶かします。溶食された石灰岩が広がるところでは、独特な地形が形成されます。
ところで、カルスト地形という名前は、スロベニアのカルスト地方からきています。スロベニアでは、カルスト地形が発達していて特徴ある地形が形成されています。

スロベニア西部で撮った写真です。石灰岩がみられます。
とある村に行ったときに、出会った現地のひとが「きれいな川があるよ」と教えてくれたので見に行ってみると、

エメラルドグリーン~コバルトブルーのきれいな色をした川でした。石灰岩地域では、川の水がこういった色になります。
スロベニアを旅したのですが、カルスト地方は通らなかったので、カルスト地形を見ることができなかったんですよね…残念。
スロベニア南西部のカルスト地方には、カルスト地形が大きく発達して広がっています。シュコツィアン洞窟群という巨大な洞窟があります。スロベニア語では、Škocjanske jame。海外のWEBサイトから写真を転載します。

park-skocjanske-jameのサイトから転載

park-skocjanske-jameのサイトから転載
カルスト地形の色々
いろいろなカルスト地形を紹介していきます。
ドリーネ
ドリーネとは、溶食によってつくられた小さな凹地です。直径数m~数十mの大きさになります。複数のドリーネが形成した凹地をウバーレといいます。
地下の洞窟の天井が崩れて落ちて地表が陥没したものを、陥没ドリーネといいます。
カレンフェルト
カレンフェルトとは、ピナクルが林立する石灰岩の斜面や台地です。出っ張った部分のことをピナクルといいます。

山口県の秋吉台で撮った写真です。秋吉台は日本で最大級のカルスト台地で、ピナクルが見られます。

ポリエ
ポリエとは、溶食作用によってできた数十kmの平野となる大きな凹地です。
カレン
カレンとは、石灰岩が溶食作用を受けてつくられた溝状の凹地のことです。
鍾乳洞
鍾乳洞とは、地下で石灰岩の溶食作用が起こって形成された洞窟のことです。
山口県の秋吉には、鍾乳洞もあります。

石灰岩のある地帯には、鍾乳洞が見られます。岩手県の龍泉町、栃木県佐野市、東京の奥多摩町、岡山県井倉洞など日本の各地にあります。
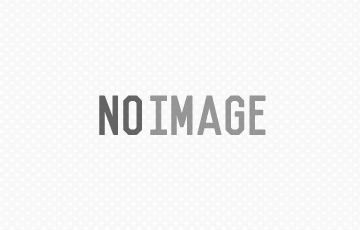










コメントを残す